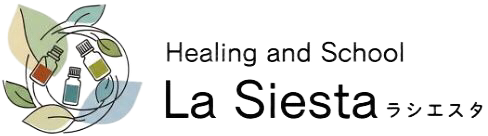こんにちは。柏のアロマテラピースクール&サロン「ラシエスタ」の白鳥です。
「夏なのに体がだるい…」「冷たいものを控えているのにお腹がひんやりする」「胃腸の調子が優れない」 もしあなたがそんな症状を感じているなら、それは「飲食冷え」かもしれません。
実は、ラシエスタが考える4つの冷えタイプのうち、この「飲食冷え」は特に夏の季節に多く見られる症状です。暑い夏でも、冷房や冷たい飲食物の摂りすぎで、知らず知らずのうちに胃腸などの内臓が冷え切ってしまうことがあります。この内臓の冷えは、全身のだるさや消化不良など、様々な不調を引き起こす大きな原因となるのです。
この記事では、飲食冷えのメカニズムとその特徴を詳しく解説。さらに、今日からご自宅でできる内臓を温めるセルフケアのヒント、そして柏のアロマテラピーサロン「ラシエスタ」で体験できる専門的なケアについてご紹介します。
内臓を温めることは、冷えにくい体質への第一歩。この記事を読み終える頃には、あなたの体を内側から温め、心地よい変化を感じるヒントが見つかるはずです。どうぞ最後までご覧くださいね。
1.あなたの冷えはどのタイプ?「飲食冷え」の正体

ラシエスタが考える4つの冷えタイプのうち、特に夏の季節に多く見られるのが「飲食冷え」です。これは、冷たい飲食物の過剰摂取や、体を冷やす食材を摂りすぎることで、体の内側、特に胃腸などの内臓が冷えてしまうタイプの冷えを指します。
なぜ「飲食冷え」が起こるのでしょうか?私たちの体は、食べたものを消化・吸収するために、胃や腸に多くの血液を集めて活動しています。しかし、冷たいものや生ものばかり摂りすぎると、内臓が冷え、その活動が鈍ってしまいます。すると、本来内臓に集まるはずの血液が滞り、全身の血行も悪化。結果として、体全体が冷える感覚に陥るだけでなく、内臓の機能低下を招いてしまうのです。夏の暑さでついつい冷たいものに手が伸びがちですが、それが実は体にとって大きな負担になっている可能性があります。
あなたは「飲食冷え」のサインを感じていませんか?以下のチェックリストで確認してみましょう。
あなたの「飲食冷え」の特徴チェックリスト
- 毎日、冷たい飲み物や食べ物を摂ることが多い(アイス、かき氷、冷たいビールなど)
- 夏でも、冷房の効いた室内に長時間いることが多い
- お腹を触ると冷たいと感じる
- 便秘や下痢をしやすい、お腹の調子が不安定
- むくみやすいと感じる
もし当てはまる項目があったら、あなたの冷えは食生活が原因かもしれません。この飲食冷えを放置せず、内臓を温める意識を持つことが、快適な毎日への第一歩となります。
2.「飲食冷え」が引き起こす体のサイン

「飲食冷え」は、単に「お腹が冷たい」という感覚だけで終わるものではありません。内臓が冷え、機能が低下することで、体には様々な不調のサインが現れます。
なぜなら、冷え切った内臓は、本来の活発な働きをすることができません。消化吸収が悪くなるだけでなく、血液やリンパの流れも滞りがちになり、全身に影響を及ぼすからです。
たとえば、以下のようなサインに心当たりはありませんか?
身体のサイン
消化器系の不調(胃もたれ・下痢・便秘)
内臓が冷えると、胃や腸の働きが鈍くなり、食べたものがうまく消化・吸収されにくくなります。その結果、胃もたれや消化不良、便秘や下痢といった胃腸のトラブルが頻繁に起こるようになります。
その結果、胃の背中側が重だるくなり、猫背になってしまいます。
全身のだるさ・疲労感
内臓機能の低下は、食べたものからエネルギーを作り出す効率も悪くします。そのため、全身のエネルギー生産が滞り、体が重く感じたり、疲れやすくなったりといった「夏バテ」のようなだるさや疲労感が続く原因にもなります。
また、体調が優れないことから姿勢が悪くなる傾向も。姿勢が悪くなると呼吸が浅くなり、酸素が全身に十分に行き渡らなくなることで、さらにだるさを感じることが出てきます。
むくみやすい体質
胃腸の機能が低下すると、むくみが出やすくなります。通常、胃に入った水分はスムーズに腸に送られますが、胃が弱っていると水分を送り出す力がなく、胃に水分が停滞してしまいます。この水分が全身に影響し、むくみの原因となるのです。
特に、舌がむくんで歯形がついている時は、胃が冷えているサインかもしれません。むくみのほかにも、だるさやめまいを引き起こすこともあります。
肌荒れや免疫力の低下
腸は「第二の脳」とも言われ、免疫機能や肌の健康と深く関わっています。内臓の冷えによって腸内環境が悪化すると、肌荒れが起きやすくなったり、風邪を引きやすくなるなど、免疫力の低下にも繋がる可能性があります。
手足の冷え
内臓が冷えると、体は体幹部(内臓)を温めようとするため、末端の手足への血流が犠牲になることがあります。また、全身の血行不良も相まって、手足の冷えが悪化することもあります。
これらの症状は、あなたの体が食生活の見直し、そして内臓を温めるケアを求めている大切なサインです。どうか、これらのサインを見逃さないようにしましょう。
3.今日から実践!内臓を温める「飲食冷え」を和らげる自宅ケア

「飲食冷え」を根本から改善し、内臓を温めるには、日々の食生活や生活習慣を見直すことが非常に効果的です。今日からでも実践できる具体的なケア方法をご紹介します。
【食事編】内臓を温め、内臓を労わる食生活
「飲食冷え」を根本から改善し、内臓を温めるには、日々の食生活の見直しが非常に効果的です。猛暑の長い夏、冷房の中で過ごすことがほとんどの私たちは、すでに体全体が冷えやすい状態。そのうえ暑いからと言って、アイスやキンキンに冷えたビールなど冷たいものばかり飲食していると、消化機能が落ち、内臓はさらに冷え切ってしまいます。
今日から意識して取り入れたい食生活のヒントをご紹介します。
意識的に「温かい飲み物・食べ物」を摂る
冷たいものばかり飲むことの多い夏こそ、意識して1日1回は温かい飲み物を摂りましょう。
特に朝は内臓が冷えているため、熱いお茶やお味噌汁を摂ることをおすすめします。お味噌汁には、リラックスホルモン「セロトニン」の元となるトリプトファンというアミノ酸が含まれているので、朝に内臓を温めると同時に心もほぐしてくれます。 私自身も、日中冷房の効いたオフィスで過ごす際には、常に温かいお茶を飲むようにしています。だるさを感じた時など、その効果を実感しています。
冷たいものを摂る際も、少しずつ口に含んだり、常温に戻してから飲むなどの工夫が大切です。
体を温める「辛い物」も上手に取り入れる
生姜、ワサビ、唐辛子など、体を温める作用のある辛い物を食事に取り入れるのも効果的です。また、食中毒が起こりやすい時期ですので、生姜やワサビなどが持つ殺菌作用は、この時期の健康維持にも役立ちます。
身体を冷やす食材は「状況に応じて」調整
トマト、きゅうり、ナス、スイカなど、夏の旬野菜や果物には体を冷やす作用があるものも多いです。
もし、冷房の中で過ごす機会が少なく、外で体を動かすことが多いようでしたら、これらの食材を積極的に取り入れて体をクールダウンするのも良いでしょう。
しかし、冷房の中でほとんど一日過ごしている場合は、加熱できるものはできるだけ温めて食べるようにしましょう。
積極的に発酵食品で内臓を温める腸活
味噌、納豆、漬物、ヨーグルトなどの発酵食品は、腸内環境を整え、内臓機能をサポートします。腸が元気になることで、体全体が温まりやすくなり、内臓を温めることに繋がります。
白砂糖はNG
砂糖が多く含まれた食べ物や飲み物(清涼飲料水、甘いお菓子など)は、体を冷やすだけでなく、血糖値の急激な上昇・下降を引き起こし、疲れやすさや自律神経の乱れに繋がると言われています。内臓の冷えの改善だけでなく、心身のバランスのためにも、できるだけ避けるように心がけましょう。
甘味は、オリゴ糖やキビ糖、みりん、はちみつなどで摂りましょう。
【生活習慣編】内臓を優しく温める習慣
毎日の習慣に少しの工夫を取り入れることで、内臓を温める効果をさらに高めることができます。
腹巻NG、寝る前にホットパック
夏に腹巻をする方もいらっしゃいますが、汗をかきやすい季節はかえって汗で体が冷え、内臓の冷えを招くこともあるため注意が必要です。 そこでおすすめなのが、寝る前にホットパックでお腹を温める方法です。
温かいタオル(濡らしてレンジで温めたものなど)をお腹に乗せて、じんわりと温めましょう。たった1分でも大丈夫。リラックス効果も高まり、安眠にも繋がります。
アロマオイルで腹部マッサージ
お風呂上がりや寝る前など、リラックスした時間にアロマオイルを使った腹部マッサージを取り入れてみませんか?
ジンジャーやオレンジ、マジョラムなど、体を温めたり、消化器系の働きをサポートしたりする精油を1%程度の濃度で植物油(ホホバオイルなど)に希釈し、お腹を優しくマッサージします。
マッサージ方法に神経質になる必要はありません。精油成分が浸透していくことでお腹の緊張が解けて温まり、安眠効果も期待できます。
適度な運動で内臓を活性化
運動は全身の血行を促進し、内臓を温める効果にも繋がります。特におすすめする運動は、軽いストレッチです。
特に腹部や腰回りを伸ばすストレッチは、内臓の動きを活発にするためにも積極的に行いましょう。無理のない範囲で、体を動かす習慣を身につけることが大切です。
4.ラシエスタの根本ケアで「飲食冷え」を根本改善

日々の食生活の見直しや自宅でのケアは大変重要であり、すぐにでも実践していただきたいことです。
しかし、長年の習慣によって蓄積された「飲食冷え」を根本から見直し、体質改善を目指すには、プロの専門的な施術で深部からアプローチすると、より効率的に内臓を温め、本来の健やかな状態を取り戻すことができます。
柏のアロマテラピーサロン「ラシエスタ」の【9月30日までの期間限定】「夏冷え対策|足とお腹の温活アロママッサージ90分」は、特に「飲食冷え」に悩む方におすすめです。
ラシエスタの施術が「飲食冷え」を根本改善する理由
柏のアロマテラピーサロンでは、単に体を温めるだけでなく、飲食冷えのメカニズムを理解し、内臓機能に特化したアプローチで改善へと導きます。
「飲食冷え」に特化した冷えタイプ診断とカスタマイズ
丁寧なカウンセリングであなたの食生活やライフスタイルをお伺いし、「飲食冷え」の根本原因を特定します。そして、特に内臓を温めること、消化器系の働きをサポートすることに重点を置いた、あなただけの施術プランを組み立てます。
内臓温活を促す「厳選アロマブレンド」
ジンジャー、フェンネル、カルダモンなど、消化器系の働きをサポートし、内臓を内側から温める効果が期待できるアロマオイルを厳選して使用します。
お客様の体調や嗅覚に合わせて最適なブレンドをご提案いたしますので、アロマ初心者の方もご安心ください。香りの力で心身ともにリラックスし、内臓の緊張を解き放ちます。
お腹への「温感アロマリンパマッサージ」の徹底
飲食冷えで冷え切った内臓、特に胃腸周りには、温かいアロマオイルを使用し、優しく、しかし丹念にリンパマッサージを行います。これにより、滞りがちな血行を促進し、内臓機能の活性化を目指します。
じんわりとした温かさが深部まで届き、胃腸の働きが活発になるのを実感していただけます。
足元から温める「温感アロマフットバス&足リフレ」
飲食冷えに伴う末端の冷えにもアプローチするため、まずは足元から温感アロマフットバスでじっくりと温めます。その後、足裏の反射区を刺激する足リフレで、全身の巡りを促進。
特に胃腸などの内臓機能の活性化をサポートし、全身の内臓を温める効果を高めます。
内臓を温めることに特化した自宅ケアアドバイス
施術後は、効果を持続させるために、あなたの飲食冷えタイプに合わせた食生活の見直しや、ご自宅で簡単にできる腹部マッサージ、内臓を温める食材の取り入れ方など、具体的な温活習慣のアドバイスシートをお渡しし、継続的な改善をサポートします。
この夏、柏のアロマテラピーサロン「ラシエスタ」で、プロのケアによって内臓を温め、「飲食冷え」で弱った内臓をケアしませんか?
5.まとめ:この夏こそ、内臓を温めて健康レベルを上げませんか?

「飲食冷え」は、夏の隠れた不調の大きな原因の一つであり、放置すると胃腸のトラブルや全身のだるさが慢性化し、快適な生活を送ることが難しくなってしまいます。
しかし、ご安心ください。内臓を温める意識とケアを取り入れることで、この「飲食冷え」は改善できます。
この夏、柏のアロマテラピーサロン「ラシエスタ」の専門的なケアと、ご自宅での温活習慣を組み合わせることで、あなたの体を内側から温め、元気で軽やかな体を取り戻しませんか?
内臓を温めることは、単に冷えを解消するだけでなく、消化吸収の向上、免疫力のアップ、疲労回復など、あなたの健康レベルを上げることに直結します。
【初回限定価格】90分 ¥11,000(税込)で体験いただけます。
9月30日までの期間限定メニューですので、この機会をお見逃しなく。ご予約は下記サイトから!
ホットペッパービューティー
オンライン予約に便利!最新のキャンペーン情報もこちらでチェック
ワンモアハンド
詳細なコース内容や、生活に役立つメルマガ配信もこちらから。こちらのサイトの方がややお得です。
【同時募集】
柏のアロマテラピーサロン「ラシエスタ」では、心と体のケアを専門に行うことのできるアロマセラピストの育成にも力を入れています。
「私自身も、誰かの心と体に寄り添いたい」「アロマの知識を深め、プロとして活躍したい」とお考えの方、ぜひ当スクールで一緒に学びませんか?
ご興味のある方は、下記のスクールページで詳細をご覧ください。
関連記事
- ホルモンバランスが招く「のぼせ冷え」を改善!夏の温活アロマケア
- ストレスで冷えやすい方へ|自律神経を整える「緊張・ストレス型冷え」のケア方法
- デスクワークで体がだるい方へ|運動不足が招く「筋肉低下冷え」の改善策
- 夏のイライラ対処法、アロマとリフレでクールダウン
- 夏の隠れ冷えを徹底ケア!9月限定温活アロマ
- 日々の疲れを癒すアロマテラピーケアの力