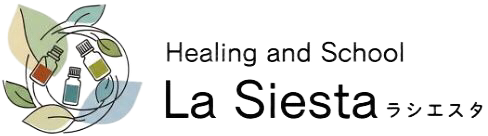現在、アロマテラピー(芳香療法)は、メディカルアロマテラピーとして、心療内科や精神科のメンタルケアや産婦人科での使用、アトピー性皮膚炎や神経性の痛みやしびれなどに利用される例が多くなりました。
お子さんの起立性調節障害に悩む親御さんも、アロマテラピーを取り入れ始めている例が増えてきました。
今回のブログでは、不登校の背景にある起立性調節障害に、なぜアロマテラピーが効果的なのか、科学的な視点からその仕組みを解き明かします。
お子さまの心と体を支える、科学的なアロマアプローチを学んでみましょう。
お子さんが飛び切りの笑顔で、学校生活を送れることを願って心を込めて書きました。
どうぞ最後までご覧になり、お子さまの支えになってあげてください。
科学的な仕組みを知った上で、お子様のデリケートな心身にアプローチする方法を学びたくありませんか?
まずは専門家から、根拠に基づいたアロマテラピーの基礎を体験してみましょう。

1.科学が証明する!香りが脳と体に与えるメニズム

この章では、アロマテラピーが心と体にどのように作用するのか、その科学的なメカニズムを分かりやすく解説します。
専門的な内容は当スクールの本コースでじっくり学んでいただけますが、ここではアロマの不思議な力を理解するための第一歩として、その概要を捉えてみてください。
香りが脳へ届く「嗅覚の伝達経路」とは?
精油の香りを吸い込むと、香り分子は鼻の奥にある嗅細胞から電気信号に変わり、脳へと直接送られます。この信号が向かう先は、思考や理性を司る「大脳新皮質」ではなく、私たちの本能や感情を司る「大脳辺縁系」です。
これは、アロマの効能を知らなくても効果が得られる理由でもあります。香りは、私たちの意識を介さず、本能の部分に直接働きかけるのです。
もしお手元に精油があれば、ぜひ一度香りを嗅いでみてください。気分がほんの少しでも変わるのを感じられるでしょう。
感情や記憶を司る「大脳辺縁系」との深いつながり
大脳辺縁系は、私たちの心身に大きな影響を与える重要な役割を担っています。ここには、以下のような機能を持つ中枢が含まれています。
- 記憶を司る「海馬」
- 感情を司る「偏桃体」
- 自律神経の中枢の「視床下部」
- ホルモンの司令塔の「下垂体」などがここに含まれます。
私たちの生体機能を司る大切なコンピュータールームのようなものです。
たとえば、リラックス効果で知られるラベンダーの香りを嗅ぐと、その香り成分が「扁桃体」に届き、セロトニンの分泌を促したり、脳内のGABAの働きを助け、リラックス効果を高めることが科学的に示唆されています。これらの物質は、気分を安定させ、心身をリラックスさせる働きがあるため、香りを嗅ぐだけで穏やかな気持ちになるのです。
「えっ、私ラベンダーの香りでリラックスしないんだけど!」という人は、本物のラベンダーの精油ではないようです。人工的に作られた「偽物」です。または、粗悪なものです。
質の高いアロマテラピーを行うには、成分が明確な「本物の精油」を選ぶことが不可欠です。市場には合成香料や不純物を含む製品も出回っているため、成分表を確認し、信頼できるものを選びましょう。
自律神経のバランスを整える香りの力
アロマテラピーの最大の効果の一つは、自律神経のバランスを回復させることにあります。自律神経は、私たちの心臓や消化、体温調節など、意識しないで行われる生命活動をすべてコントロールしています。自律神経のバランスが整えば、多くの不調は改善に向かうと言っても過言ではありません。
自律神経の働きは、こちらの本がわかりやすいです。
➡「結局、自律神経が全て解決してくれる」/小林弘幸先生著
もちろん、ウォーキングや食事、サウナも自律神経の回復に役立ちます。しかし、不登校や起立性調節障害のお子さんに、急な運動習慣や食生活の変更を強いるのは難しいでしょう。
アロマテラピーは、嗅ぐだけで手軽に始められ、効果を感じやすいという大きなメリットがあります。お子さんにとって無理のない方法で、心身のバランスを整える手助けをしてくれるのです。
2.不登校・起立性調節障害に特化!アロマテラピーの最新研究事例

不登校の背景には、心身の不調が隠れていることが少なくありません。特に、起立性調節障害(OD)は、立ち眩み、朝の起床困難、頭痛といったつらい症状を伴い、昼夜逆転の生活を引き起こすこともあります。
これらの症状に対し、アロマテラピーがどのようにアプローチできるのか、具体的な科学的知見を基に見ていきましょう。
*不登校と起立性調節障害の関係性については、以下の記事で詳しく説明しています。
事例1:ストレスホルモン(コルチゾールの減少効果)
コルチゾールは、「ストレスホルモン」とも呼ばれ、ストレスから体を守るために欠かせないホルモンです。しかし、不登校の子どもたちが抱える長期的なストレスや複数のストレス要因にさらされ続けると、コルチゾールが過剰に分泌され、心身に大きな負担をかけます。
科学的研究では、アロマテラピーがこのコルチゾールの過剰な分泌を抑制する効果が示唆されています。
ゼラニウム
ゼラニウムに含まれるゲラニオールなどの成分が、副腎皮質に働きかけ、コルチゾールの分泌を調節する作用が報告されています。これは、副腎の過剰な働きを落ち着かせ、心身をリラックス状態へ導くことにつながります。
フランキンセンス
フランキンセンスの深い香りは、呼吸を深くし、心拍数を落ち着かせる効果があります。これにより、副交感神経が優位になり、リラックス状態へと導くことで、間接的にコルチゾールの分泌を抑制する効果が期待できます。
これらのアロマは、過剰なストレス反応を和らげ、自律神経のバランスを整えることで、起立性調節障害(OD)の症状が強く現れる朝の不調を軽減する助けとなるでしょう。
事例2:睡眠の質向上と心身のリラックス
不登校のお子さんが抱える最も大きな課題の一つが、睡眠の質の低下や昼夜逆転です。
深い睡眠は、心身の疲労回復や精神的な安定に不可欠であり、規則正しい生活リズムを取り戻す第一歩となります。栄養を見直すことと並行してアロマテラピーを取り入れることで、非常に高い効果が期待できます。
アロマテラピーが睡眠に与える効果は、科学的にも広く研究されています。
ラベンダー
ラベンダーの主成分であるリナロールは、脳の活動を穏やかにし、不安を和らげる作用があることが示されています。
ある研究では、就寝前にラベンダーの香りを嗅ぐことで、ノンレム睡眠(深い睡眠)の時間が平均で20%増加したという報告もあります。これは、質の良い睡眠がもたらす心身の回復に直結します。
ベルガモット
柑橘系の爽やかな香りで知られるベルガモットには、鎮静作用を持つ成分が含まれており、特に就寝前のリラックスに効果的です。研究では、ベルガモットの香りが心拍数を平均10%低下させ、ストレスや緊張感を和らげることが示されています。
就寝前にディフューザーで香りを拡散したり、アロマスプレーを枕元に吹きかけたりする簡単な方法でも効果が期待できます。これらのアロマを日常に取り入れることで、お子さんの睡眠リズムを整え、心身ともに健やかな状態へと導く手助けとなるでしょう。
事例3:集中力や意欲の向上への影響
周囲からは「怠惰」と見られがちな不登校や起立性調節障害のお子さんは、意欲や集中力の欠如を抱えていることが少なくありません。こうした心身の停滞感に、アロマテラピーがどのように働きかけるのか、見ていきましょう。
意欲を高めるローズマリー
ローズマリーの香りは、心拍を上げ、血圧を上昇させることで、心身を活動的にする働きがあることが知られています。これは、ローズマリーに含まれる主成分である1,8-シネオールなどが、脳の特定の領域を刺激し、神経伝達物質の放出を促すためです。
集中力向上
ある研究では、ローズマリーの香りを嗅ぐことで、集中力や記憶力が向上したという結果が報告されています。これは、特に午前中に集中力が続かない起立性調節障害のお子さんにとって、学習や活動への意欲を取り戻す助けとなります。
血圧上昇作用
不登校のお子さんは低血圧であることが多く、このことが朝の倦怠感や立ちくらみの原因となることがあります。ローズマリーの香りが血圧を穏やかに上昇させる作用は、朝の体調を整える上で重要なサポートとなります。
神経強壮剤「タイム」の役割
一度学校へ行かなくなると、再び一歩踏み出すには大きな勇気が必要になります。タイムは、その強壮作用から「勇気のアロマ」とも呼ばれています。
タイムに含まれるチモールなどの成分は、神経系に働きかけ、心身の活力を高める効果が期待できます。特に、神経が疲弊し、心身のエネルギーが枯渇した状態の回復を助ける作用があるため、新しい一歩を踏み出すための精神的なサポートとして役立ちます。
これらのアロマを上手に活用することで、心身のバランスを整え、お子さんが再び前向きな気持ちで過ごせるよう導くことができるでしょう。
3.科学的根拠に基づく、アロマの安全な使い方と選び方

アロマテラピーは、心身の健康に役立つ強力なツールですが、その効果を最大限に引き出し、安全に活用するためには、正しい知識が不可欠です。この章では、科学的な知見に基づいた、アロマの選び方と活用法について解説します。
お悩み別!プロが選ぶおすすめアロマオイル
前の章で解説した科学的根拠に基づき、不登校のお子さんが抱えるお悩み別に効果が期待できる精油をご紹介します。
ただし、コレが正解というわけではなく、お子さんのお好みを優先してください。なぜなら、香りの好みは体内の状態を表す指標だからです。
朝の辛さに
- 血圧をあげてスピリットを高める「ローズマリー」。ローズマリーは、自信を立負けるハーブとして古くから処方されてきた歴史があります。虚弱な体質のお子さんに有効です。
- 脳を明瞭にする「レモン」。酸味が特徴のレモンの香りは、思考の混乱を収め、不安を和らげます。
不安や緊張に
- リラックス作用が高い「ラベンダー」。ラベンダーは、自己表現が下手で生きにくさを感じているお子様の心を楽にしてくれます。鬱積した感情を開放してくれるので、気分がとても和らぎます。
- 呼吸を深める「フランキンセンス」。フランキンセンスは心が乱れて、不調和音を感じているときにイライラを開放してくれます。
意欲低下に
- 心を鎮静させて、高揚させる「ベルガモット」。ベルガモットは抑圧された感情を開放し、自発性を取り戻してくれます。
- 心身のバランスをとる「ゼラニウム」。ゼラニウムは、完璧主義を手放し、情緒豊かな心を回復させてくれます。
集中力に
胃腸の働きを高める「ペパーミント」。胃腸が弱い人には集中力の欠如が見られます。ペパーミントは、食べものの消化にとどまらず。新し考えや思考の消化をも促進してくれます。新しい一歩を踏み出す手助けになります。
集中力を高める「ローズマリー」。心拍を高めて血流を促すローズマリーは、脳への血流量も増加させ、集中力と神経衰弱に役立ちます。
夜の安眠に
安眠効果の高い「ラベンダー」。静かな落ち着きをもたらし、リズム障害を改善してくれます。
温かさをもたらす「スィートオレンジ」。ストレスや欲求不満が過剰になり寝付けないときに、楽観的な気分を促してくれます。
誰でもできる!効果的なアロマ活用法
芳香浴
ディフューザーやアロマストーンを使うこともよいですが、もっと気楽に利用しましょう。
小さなシリコンカップに濡れティッシュを置き、そこに精油を垂らします。自分のすぐそばに置けますし、リビングや寝室などに数個置いて、いつでも香りが漂うようにすることもできます。
アロマスプレー
精油と精製水などを混ぜて、オリジナルのアロマスプレーを作ります。枕元や部屋に吹きかけることで、手軽に香りを楽しむことができます。
数種類の精油を混ぜて使ってもOK.
アロマバス
湯船に精油を数滴垂らして入浴する方法です。心身の緊張を解き、深いリラックス効果をもたらします。
湯船に入る習慣をつけるためにも、アロマの香りを利用するとよいでしょう。
自己流は危険?専門家から学ぶことの重要性
- 精油の品質: 偽物や粗悪な精油は、期待する効果が得られないだけでなく、健康を害する可能性もあります。信頼できるブランドの、成分が明確な「本物」の精油を選びましょう。
- 適切な使用法: 精油の濃度や使用方法は、年齢や体質、お悩みの内容によって異なります。誤った使い方をすると、肌トラブルや体調不良の原因となることがあります。
- 正しい知識の習得: アロマテラピーは奥が深く、専門的な知識が必要です。特に、不登校支援のようにデリケートな問題にアプローチする場合は、体系的な知識を学ぶことが不可欠です。
【科学的アプローチをすぐに実践!】
➡専門家から学ぶ!不登校支援アロマアプローチの1DAY講座をチェック

まとめ:アロマを不登校支援に活かす

本記事では、不登校や起立性調節障害のお子さんに、なぜアロマテラピーが有効なのか、科学的な根拠を元に解説しました。
単なる「いい香り」としてではなく、脳科学や生体機能に働きかける確かな根拠があることをご理解いただけたかと思います。
アロマテラピーは、心身に深く関わるデリケートなアプローチです。そのため、単に知識を詰め込むだけでなく、お子さん一人ひとりの状態に合わせた、安全で適切なアロマの選び方や活用法を学ぶことが不可欠となります。
お子さんの心に寄り添い、本当の笑顔を取り戻す手助けをしたいと願うあなたへ、私たち専門家がその道をサポートします。
1DAY講座:「不登校支援のためのアロマアプローチ講座」のご案内
本記事でご紹介した科学的根拠や実践法を、さらに深く、体系的に学びませんか?
当スクールの1DAY講座では、不登校支援に特化したアロマテラピーの知識を、経験豊富な講師から直接学ぶことができます。
- 科学的根拠に基づいた専門知識
- 個別のお悩みに合わせた実践的なアプローチ
- お子さんと安全に楽しむための正しい使用法
この講座は、お子さんの心身を深く理解し、アロマテラピーを通じて前向きな変化を引き出すための、確かな一歩となるでしょう。
お子さんの笑顔を取り戻したいと願うすべての方へ
不登校は、お子さんだけでなく、ご家族にとってもつらい経験です。
しかし、アロマテラピーという優しいツールを使うことで、心に光を灯し、ご家族みんなが笑顔で過ごせる未来を築くことができます。
どうか、一人で抱え込まず、この新しい一歩を踏み出してください。私たちは、専門家として、そして同じ親として、あなたの挑戦を心から応援しています。
科学的根拠に基づいた正しい知識こそが、お子様の心と体を守る最大の支えになります。

関連記事
- 【朝起きられない!】不登校と起立性調節障害、アロマでリズムを整える
- ストレスで冷えやすい方へ|自律神経を整える「緊張・ストレス型冷え」のケア方法
- デスクワークで体がだるい方へ|運動不足が招く「筋肉低下冷え」の改善策
- 胸のあたりがざわついた、そこでシナモンの香りを嗅いだら、、
- 【ストレスに負けない!】睡眠の質を高める呼吸法とアロマテラピーやり方