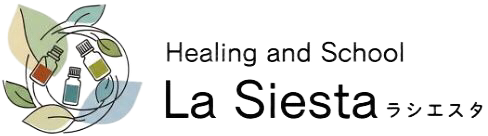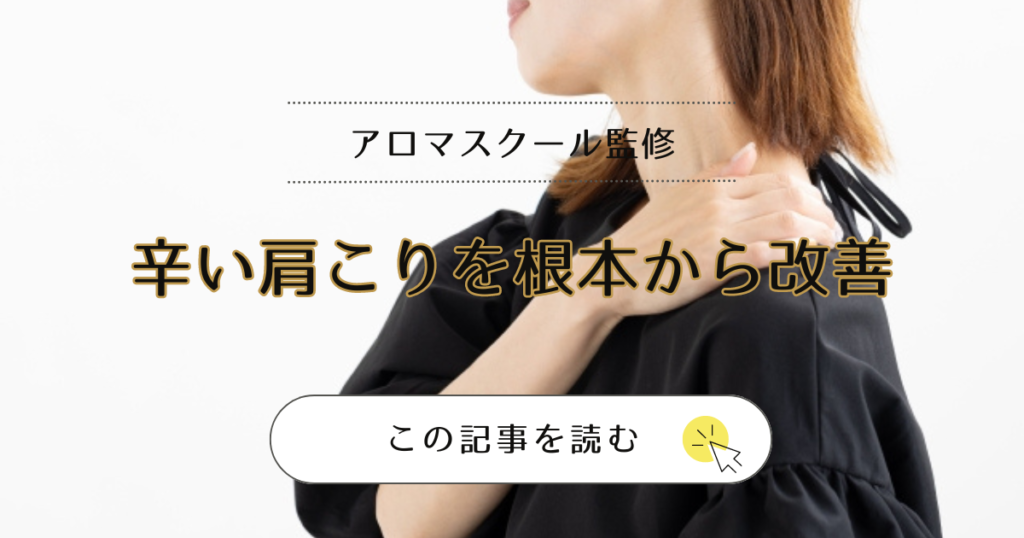辛い肩こりは、原因にマッチしたアロマレシピとアロママッサージで改善できます。
肩こりが酷くて、頭痛や吐き気にまで発展している方へ。
とにかくその辛さ、今すぐにでもどうにかしたいですよね。
とりあえず駆け込むマッサージ店。
でも、効果は一時的。
「肩こりのない身体になりたい!」とお悩みは深いかと思います。
実は、辛い肩こりは原因にマッチしたアロママッサージとアロマレシピでご自宅でも改善できます。
このブログでは、肩こりの原因に対応したアロマレシピとマッサージ方法をお伝えします。
とにかくつらい肩こり、このブログを見ながらご自宅でアロママッサージをしていただくとスッキリ楽になりますよ。
どうぞ最後まで、そして何回でも見直して実践してみてくださいね!
1.アロママッサージの効果と肩こりへのアプローチ

たくさんの肩こり解消法がある中で、アロママッサージの選択は欠かせません。
なぜなら、アロママッサージは、単なる香り付きのマッサージではなく、精油(アロマオイル)を鼻からと皮膚から体内へ吸収させ、体の中から肩こりの根本原因を改善していくからです。
後の章で示しますが、肩こりといってもその原因は様々ですし、原因が複合的な場合は多々あります。
たとえば、ある女性は、事務のお仕事で一日中パソコンで細かい数字を見ている。そうすると眼精疲労が肩こりの原因となります。
また別の女性は、緊張過多で何事にも緊張するので、呼吸が浅くなり姿勢が悪くなって肩がこります。
その原因原因で精油(アロマオイル)の選び方やトリートメント法を変えてアプローチするのです。
ですので、単なるもみほぐしとは違い、目の筋肉のこわばりをとったり、精神面で穏やかにすることで肩こりを改善していくのがアロママッサージなのです。
もちろん、もみほぐしや整体も、筋肉のこわばりをほぐしていくには効果的です。
上手なマッサージ師にお願いすると、とても心地よくほぐれていく感じがあります。また筋肉がほぐれることで心もほぐれることもあります。
しかし、アロママッサージは、精油が皮膚から血流に流されるので、その効果が持続的なものになりますし、オイルマッサージならではの心地よさは優しさに包まれる至福感があります。
要するに、アロママッサージによる肩こりへのアプローチは、以下に集約されると言えます。
- 精神的であれ、感情的であれ、内臓や筋肉の体の不調であれ、どんな原因から発する肩こりも精油の効能効果がアプローチしてくれる
- 原因によるレシピを作るので、原因毎のアプローチが可能
- オイルマッサージによる抜群の心地よさが筋肉の緊張を和らげる
では次の章からは、肩こりの主な原因と精油レシピを見ていきましょう。
2.肩こりの主な原因

肩こりの原因は様々ですが、代表的なものを以下に挙げます。
- 眼精疲労
- 腕や手の疲労
- 胃腸の不調による姿勢の悪さ
- 筋肉的疲労
- 神経の緊張
- 冷え
- 気象病
- ホルモンバランス
- 更年期
だいぶありますね。
原因毎にアプローチするアロママッサージ
これら肩こりの原因に対して、それぞれの精油でアプローチするのがアロママッサージです。
たとえば、緊張型の性格で、PC仕事が一日の大半を占める方には、
- イランイランやサンダルウッドなど催淫系の精油
- 眼精疲労を軽減し目の周りの筋肉や関節を和らげるマジョラムやラベンダー、ゼラニウムなどをブレンドします。
入念なカウンセリングから導き出す
これらの原因を探るために、アロママッサージを施す前には、入念なカウンセリングを行います。
本人が自覚していないものもあるのでセラピストから訪ねて振り返ってもらいます。
- 便通
- 痛みのある個所
- 最近気になることがあったか?
- また、生理について
- 睡眠時間や睡眠の質
- アレルギーなど
あらゆることをお聞きした上で適切なアロマレシピを作るのがアロマセラピストの仕事です。
もちろん、そこには香りの好みも入ります。
好む香りはその時々で違います。
季節やその人の置かれている環境や体の内部などにも影響するので、香りの好みは大事な要素です。
3.肩こり撃退に最適な精油の選び方

では肩こり撃退に適切な精油の選び方を具体的にご説明しましょう。
以下の順番で行うと効果的レシピが選べます。
1.慢性?急性?
いつから肩こりに悩まされているか?
- 一週間以内
- 1ヵ月
- 半年以上
2.生活環境を振り返る
- 睡眠時間
- 睡眠の質
- 毎日の便通
- 冷え(手のひらでふくらはぎを触ると冷えているかどうかわかります)
- 生理周期
3.気候、気温の変動
台風なども考慮します。
4.内観する・出来事を追う
- 我慢していなかったか?
- イラつく出来事はなかったか?
- 心無い言葉で責められていないか?
- 寂しさはなかったか?
- 今日一日、一週間を振り返って、良かったこと嫌だったことを思い返してみる
5.香りの好み
いくつかの香りを嗅いで、好みの香りを見つけます。好みの香りから原因を探る。
6.効能効果と好みの香りの照らし合わせをする
精油の効能効果から好みの香りを選びたします。次にその好みの香りの効能効果の共通点を探ります。
それがあなたの肩こりの原因です。
たとえば、先の緊張型で、PC仕事が一日の大半という女性が以下のような要素を持っているとします。
- 便秘気味
- 水分はあまりとらない
- 冷えがある
- 慢性的な肩こり
- 仕事での焦りがある
- 先輩に嫌なことを言われた
だとしたら、
イランイラン、サンダルウッド、ラベンダー、ゼラニウム、ジュニパー、サイプレス、オレンジ、ユーカリ、グレープフルーツなどの精油を嗅いでみます。
その中で、グレープフルーツ、イランイラン、ラベンダーの香りが好みだとしたら、精神的な抑圧状態が肩こりの大きな原因になっています。
もちろん眼精疲労もありますが、精神的な抑圧の方が大きいのです。
4.プロが教えるご家庭でのアロママッサージテク

さて、肩こりの原因がわかりました。
実は、肩こりの原因によってマッサージ手法も変えなくてはいけません。
ですが、ここでは、ご家庭で行うのに適したマッサージとして、それぞれの原因に応じた施術箇所とポイントを見ていきましょう。
緊張過多タイプで、PC仕事が多い肩こり
- 精油を入れた手浴をします。
- 左右の指を絡めて回し、手首をほぐします。

- 腕にオイルを塗布し、優しくなでます。
- 仰向けになり、お腹にオイルを塗布し、時計回りに優しくなでます。
育児中で腕の筋肉疲労による肩こり
- 手・腕にオイルを塗布し軽く流します。
- オイルをつけたまま手浴とひじ浴を行います。
- 腰にマッサージオイルをすり込みます。
眼精疲労と運動不足が原因の肩こり
- 脚にマッサージオイルを塗りこみます。
- 足裏にもオイルをつけてまんべんなくほぐします。
- 手の指を足の指に絡めて(差し込んで)足指を回します。
- 足指を一本ずつもみほぐします。(痛い指があれば丁寧に)
- ふくらはぎからハムストリングを上に引き上げるようにマッサージします。
- おでこを指の腹を使ってほぐします。
- 眉上をほぐします。
- 目のストレッチを行います。
ご家庭では、このように原因に沿って部分的にマッサージをすることがおすすめです。
*アロママッサージオイルのご注意
アロママッサージオイルは、必ず太白油やホホバ油に希釈してお使いください。
プロのマッサージテクニックやアロマレシピの作り方は、アロマスクールで体系的に学ぶと一生ものの力になります。
まとめ:肩こりにアプローチするアロママッサージとは?

肩こりにアプローチするアロママッサージは、原因によってレシピもマッサージ手技も違います。
まずは、原因を知ることが第一の作業です。
上記で示したように、ご自身の心や体だけでなく、気象状況などの環境も併せて考えることが良いレシピの基本ですが、これらを完璧に行なうことは難しいものです。
まずは、好みの香りを選び、アロママッサージを作ってみましょう。
患部にマッサージしながら、精油の効能を調べて、それに相応する症状が自分に当てはまらないかを見るだけでも興味深いものです。
アロマスクールに通うと、肩こりをはじめ、さまざまな身体の不調に合わせたアロマレシピやマッサージテクニックを基礎から学ぶことができます。
実際にプロのアロマセラピストが、お客様一人ひとりの悩みに寄り添い、最適なアロマオイルを選び、施術を行う様子を体験できるアロマサロンもおすすめです。
「どのアロマオイルを選べばいいの?」「どんなマッサージをすれば効果があるの?」
そんな疑問も、プロのセラピストに相談することで解決できます。
アロママッサージの方法は、症状の原因によって違うため、「これが正解!」というものはありません。
しかし、何より自分が心地よいことが一番です。
心地よいということは筋肉も神経もリラックスしているということですよね。
心地良い時間、自分を労わる時間を大切にしてくださいね。

~この記事を書いた人~
白鳥志津子
アロマテラピー専門家、自然療法家、リフレクソロジスト、カウンセラー、睡眠アドバイザー、不登校セラピスト
1998年に自身のアロマテラピーサロンラシエスタを開業し、翌年アロマテラピーの専門家を育てるアロマテラピースクールを開校。
多くのアロマセラピストを育てるとともに、第一線でクライアントのセラピーにあたる。
ストレスマネジメントを提唱し、アロマテラピーにとどまらず、食事や睡眠、運動の重要性を説いています。
ブログでは、実践的なストレス解消法やリラクゼーションテクニックに加えて、健康的な食事のアイデアや睡眠の改善方法、効果的な運動プログラムについても積極的に情報発信しています。
幅広い視点からのアプローチで、読者の心と体の健康をサポートするための具体的なアドバイスやヒントを提供しています。